ニュース
2025年8月11日、オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は、9月の国連総会においてパレスチナ国家を正式に承認する方針を表明しました。政府は声明で「この決定は、二国家解決に向けた国際的な勢いを加速させるものだ」と述べ、パレスチナ自治政府(PA)に対し、安全保障改革、ハマスの排除、非武装化、そして民主的な統治体制の確立を求めました。
補足説明
今回のオーストラリアの動きは、フランス、英国、カナダ、マルタが7月末に相次いで承認を発表した流れに続くもので、西側主要国の外交姿勢に大きな転換点をもたらしています。これまで二国家解決への支持を表明する国は主にアジア・アフリカ・中南米諸国に集中していましたが、先進民主主義国が次々に承認へと踏み切ることで、国際社会におけるパレスチナ承認の「多数派」はより強固なものになりつつあります。
歴史的にみると、パレスチナ国家の承認は以下の流れをたどっています。
- 1988年:パレスチナ解放機構(PLO)が国家宣言を発表。
- 2012年:国連がパレスチナを「オブザーバー国家」として承認。
- 2025年4月時点:国連加盟193カ国のうち147カ国(約76%)が承認済み。
- 2025年7月末:フランス、英国、カナダ、マルタが相次いで承認を表明。
- 2025年8月11日:オーストラリアが正式に承認を発表。
2025年現在、承認国は147カ国とバチカンを含み、特にアジア・アフリカ・中南米諸国を中心に支持が広がっています。今回のオーストラリアの判断は、西側諸国における承認拡大の引き金となる可能性があり、国際社会での停戦交渉や将来の和平合意に向けた枠組みに大きな影響を与えると見られています。
海外の反応
Inb4 comments asking why the minister of foreign affairs doesn’t focus more on domestic affairs
「どうせ“外務大臣は国内の問題にもっと集中すべきだ”ってコメントが来るんだろ、ってね。」
Many such instances going off previous posts here.
「この手の話、ここでも過去に何度も見かけたな。」
Maybe they thought foreign affairs meant policing foreigners.
「“外務”って、外国人を取り締まることだと勘違いしてるんじゃないか?」
It’s a pre-canned talking point.
「ああいうのはテンプレみたいな決まり文句だよ。」
The people who usually say “they should focus on Australia’s issues” tend to be the crowd who hate Muslims anyway.
「“オーストラリアの問題に集中すべきだ”って言う人たちって、大体ムスリム嫌いの層なんだよな。」
Yeah probably what they mean is let’s target Muslims in Australia first
「つまり本音は“まず国内のムスリムを狙え”ってことなんだろうな。」
I’m part of the group that wants to understand why questions. Why does the vast vast majority of religious hate attacks stem from one religion.
It’s important to protect the innocent and I don’t want this question to be used as an excuse to hate on anybody.
Innocent people who wish to live freely should be protected by the full extent of our laws.However why, I want leaders from our muslim communities to be more vocal on the matter. And really flesh out radicalism a little more pro-actively.
I am someone who’s lived in a majority muslim community for a long time. I experienced the culture, food and hospitality of muslims and it was an absolute pleasure.
Though why still burns at the back of my head, for I’ve experienced some pretty disturbing rhetoric from local leaders also. It’s what I call the middle stance of the Islamic integration in western societies. We’re a voice too and I want questions answered and hateful rhetoric eradicated from all sides of the aisle.
I will acknowledge – the rise of extreme hate from the west is without a question rising and I can’t help to think, in part is it because the middle stancers are being ignored or lapped up into the fascist corner, for merely asking concerned questions.
They hate Jews, and I mean hate them, a lot of the young ones are taught to hate, not learn for themselves.
Anyway take it from me. I love the good parts of muslim culture I wish that to be 99% I’d be happy to settle for 95%. But that is far from the numbers I’ve experienced. And yes that is subjective. I’d be very happy to be proven wrong.
「自分は“なぜ”を知りたい派なんだ。なぜ宗教に基づくヘイトの大多数が、特定の宗教から出てしまうのか。
無実の人を守るのは当然だし、この疑問が誰かへの憎悪の口実にされるのは望んでいない。自由に暮らしたい無辜の人たちは法の下で守られるべきだ。ただ、それでも“なぜ”が頭を離れない。だからこそムスリムコミュニティのリーダーたちには、もっと声を上げ、急進主義について積極的に向き合ってほしいんだ。
自分は長くムスリムが多数派の地域に住んできて、文化や食事、ホスピタリティを楽しんできた。そこは素晴らしかった。
けれど同時に、地元のリーダーから耳を疑うような過激な発言も聞いた。西洋社会でのイスラム統合の“中間層”ってやつだな。自分たちにも声があり、質問に答えてもらいたいし、憎悪の言説はあらゆる側から取り除かれるべきだと思う。
西側からの極端なヘイトも確実に増えている。ただそれは、こうした“中間層”が無視され、ただのファシスト扱いされているからなんじゃないか、とも思う。
彼らはユダヤ人を本気で憎んでいる。多くの若者が“自分で考える”前に“憎むこと”を教え込まれているんだ。
自分としては、ムスリム文化の良い面が99%を占めるようになってほしいし、95%でも満足する。それくらい好きなんだ。ただ、残念ながら自分が体験した現実はそこまでではなかった。これは主観的な意見だから、間違っていると証明してくれるなら喜んで受け入れるよ。」
Why is it always the most uneducated, illiterate people defending a genocide?
「なぜいつも“大虐殺を擁護する”のは、無教育で読み書きもできない人たちなんだろう?」
Because the the most uneducated, illiterate people consume the tabloid media that tells them to defend the genocide
「それは、そういう層がタブロイド紙を真に受けて“大虐殺を擁護しろ”と刷り込まれてるからさ。」
I’m normally a guy that jumps on that train but all good for the federal government to focus on international issues like this.
「普段なら“国内を優先しろ”って言う側なんだけど、今回は連邦政府がこういう国際問題に集中するのは悪くないと思う。」
Abiut fucking Time – Bibi is quoted as saying that Australians today would be doing exactly as Israel did.
No Bibi – we would not be shooting eight-year-olds in the head.
At least not while I’m alive.「やっとかよ。ビビ(ネタニヤフ)は“オーストラリア人だってイスラエルと同じことをするだろう”なんて言ったらしいけど…
いやいやビビ、俺たちは8歳の子どもの頭を撃ったりはしない。少なくとも俺が生きてる間はな。」
In the wake of the 2024 Melbourne synagogue attack, Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu was quoted as saying, “It is impossible to separate the reprehensible arson attack from the federal government’s extreme anti-Israeli position”.
「2024年メルボルンのシナゴーグ襲撃事件の後、ネタニヤフ首相は“あの卑劣な放火は連邦政府の極端な反イスラエル姿勢と切り離すことはできない”と発言していた。」
He will say whatever gives him more controls over the law now that his agent attorney general is out
「今や自分の代理だった司法長官がいなくなったから、ネタニヤフは法をコントロールできるようなことなら何でも言うだろうな。」
He will say whatever he can to stay out of prison. Now I think about it someone else comes to mind.
「奴は刑務所に入らないためなら何でも言うだろう。…こう考えると、別の誰かを思い出すな。」
No Bibi – we would not be shooting eight-year-olds in the head. At least not while I’m alive.
About that. We have, we just don’t do that anymore.
「いやビビ、俺たちは8歳児の頭を撃ったりはしない。少なくとも俺が生きている間はな。
…ただな、それについて言えば、俺たちも昔はやってたんだよ。ただ今はもうやらなくなっただけだ。」
Technically indigenous kids still die in custody.
「正確に言うと、先住民の子どもは今も拘留中に死んでる。」
Per arrest, they have a lower rate of death than non-Aboriginals
「逮捕件数あたりで見ると、非先住民より死亡率は低いんだよ。」
Indigenous deaths in custody are relatively low compared to the rest of the population.
Kids do go to jail still, but that’s hardly comparable.
「拘留中の先住民の死者数は、人口比で見ればそこまで多くはない。子どもが刑務所に行くことはあるけど、イスラエルのケースとは比べものにならないよ。」
Technically that’s not evidence they’re being shot in the head, it’s more often they bash each other to death or they die during arrests. Also it’s rare as fuck for any kid to die in custody including indigenous kids it’s only really ever adults, and still no difference to non indigenous deaths in custody
「“頭を撃たれて死んでる”って証拠はない。実際には殴り合いで死んだり、逮捕中に亡くなるケースが多い。子どもが拘留中に死ぬのは極めて稀で、先住民でも例外じゃない。むしろ大人のケースがほとんどで、非先住民との差もあまりない。」
Well, we did go to Iraq to fight a country that did nothing to us.
「でも俺たち、何もしてない国イラクに戦争しかけたよな。」
And decent Australians protested that shit, too.
「でも、まともなオーストラリア人はちゃんとあの戦争に反対してた。」
Yes we have genocide in our past bibi but that doesn’t mean we are actively going to murder people the way israel is
「確かに俺たちにも過去にジェノサイドの歴史はあるさ。でもだからって、イスラエルみたいに今も積極的に人を殺すわけじゃない。」
I mean- we kind of did to the indigenous population which is why Palestine is such an issue for Australia.
「いや、実際俺たちも先住民にはやっただろ。それがあるからこそ、パレスチナ問題はオーストラリアにとって大きな意味を持つんだ。」
We did in the past and we will not do it again. That’s the difference I hope.
「俺たちは確かに過去にやった。でも二度と繰り返さない。それが違いだと信じたい。」
We can at least start by denying foreign repeats of our own sins.
「少なくとも、自分たちが過去に犯した罪を外国で繰り返すのを止めることから始めよう。」
What? The Bedouin are the indigenous people of Israel. The vast majority of those in Israel live outside of the occupied territories. They’re Israeli.
「何言ってんだ?ベドウィンはイスラエルの先住民だぞ。しかもイスラエル国内の大多数は占領地の外に住んでる。彼らはイスラエル人なんだ。」
Indigenous Australians have full sovereign rights, full protection of Australian law, voting rights and citizenship, not to mention individual Indigenous services and benefits.
Palestinians are essentially the Indigenous of the Levant and live like 4th class citizens with no sovereignty or citizenship rights
「オーストラリアの先住民は完全な主権を持ち、法の保護や参政権、市民権を持っている。それどころか個別の支援や優遇措置だってある。
でもパレスチナ人は、レバントの先住民と言える存在なのに、主権も市民権もなく“四等市民”のように扱われている。」
unfortunately comparison remains valid.
australia has segregation in law (eg NTER) rendering many Indigenous australians as second-class citizens. The ‘Indigenous services and benefits’ you describe actually displace mainstream service provision, so that Indigenous clients live with second-rate standards re basic provision of housing, health and education. Indigenous cultures in australia remain under threat by numerous pressures.
「残念ながらその比較は妥当だ。オーストラリアにはNTER(先住民特別法)みたいな差別的な法律があって、多くの先住民を“二級市民”扱いにしている。
君の言う“支援や優遇措置”は、実際には普通のサービスを置き換えてしまって、先住民は住宅・医療・教育の基本的水準で二流の待遇を受けているんだ。オーストラリアの先住民文化は、今も多くの圧力で脅かされ続けている。」
オーストラリアのパレスチナ国家承認が示す転換点
西側外交の分岐点:米国一辺倒からの変化
オーストラリアがパレスチナ国家を承認する方針を打ち出したことは、西側諸国の外交姿勢にとって大きな転換点になり得ます。これまで米国の慎重な立場を意識して承認を避けてきた国々にとっても、「豪州が動いたのなら自分たちも」という心理的な後押しになる可能性があります。
二国家解決の条件は高いハードル
ただし承認が実際の和平や国家建設に直結するかどうかは別問題です。オーストラリアは、ハマスの排除や非武装化、民主的な統治といった条件を付けています。これは理想的な目標である一方で、パレスチナ自治政府にとっては非常に厳しいハードルです。もしこれらが進まなければ、承認は「象徴」にとどまり、実質的な変化を生み出せないリスクもあります。
イスラエルの孤立と外交圧力
国際的には、イスラエルの孤立感が一層高まることが予想されます。米国は引き続き最大の同盟国であるものの、欧州や英連邦諸国が次々と承認に踏み切れば、イスラエルは交渉に復帰せざるを得ない圧力に直面します。その一方で、対話に応じなければ「国際社会での孤立」が進んでしまう可能性もあります。
インド太平洋への影響
今回の決断は、中東問題にとどまらずインド太平洋の外交にも波及しそうです。オーストラリアは米国主導の対中戦略の要ですが、今回のように独自判断を示すことで「米国追随一辺倒ではない」とアピールした形になりました。ニュージーランドやASEANの一部諸国、韓国なども、これを機に同じ問題に対するスタンスを考え直すかもしれません。
国連外交と「数の正当性」
すでに国連加盟国の約4分の3がパレスチナを承認していますが、これまでは「グローバルサウス中心の動き」と見られてきました。そこにオーストラリアのような先進国が加わることで、「多数派の正当性」は一段と強まります。今後の国連での停戦決議や人道支援、和平枠組みの形成にも影響を与えていくでしょう。
更に詳しく知りたい方へ
『イスラエルとパレスチナ 紛争の解剖学』
長年にわたって続く中東の対立を歴史的・政治的に丁寧にひも解いた一冊です。著者のトマ・スネガロフはフランスの歴史学者で、複雑に絡み合う宗教・領土・国際政治の要素を「なぜ紛争が終わらないのか」という問いに沿って整理しています。
ニュースを追うだけでは見落としがちな背景を学べるため、今回のオーストラリアによるパレスチナ承認のニュースを理解する上でも役立ちます。国際政治や地政学に関心のある方はもちろん、「イスラエルとパレスチナの関係を一度体系的に整理してみたい」という方におすすめの入門書です。
サクッとわかる ビジネス教養 新地政学
イラストや図解をふんだんに使って、地政学の基本から最新の国際情勢までをわかりやすく解説した一冊です。イスラエル・パレスチナ情勢、ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、アメリカ国内の分断といった「今まさに動いている地政学リスク」も取り上げられており、ニュースを追う際の理解が一段深まります。
初心者や「地政学をざっくり知りたい」という方にぴったりで、外交ニュースを記事で読む人にとっても入門書として最適
世界最強の地政学(2024年4月刊)
「地政学」を単なる地理的な知識にとどめず、大国がどう戦略を立て、パワーバランスを動かしてきたのかを徹底的に解剖した本です。シーパワーとランドパワーの対立やグランド・ストラテジーの考え方を軸に、米中対立、ロシアの軍事行動、ヨーロッパや中東をめぐる動きなどを歴史と照らし合わせながら整理しています。
より実践的・戦略的に「世界がなぜこう動いているのか」を理解したい中級者以上の読者におすすめです。
総括|象徴から実質へ進めるかどうか
今回のオーストラリアの承認は、西側諸国にとって「象徴」にとどまらず「実質的な政策転換」になる可能性を秘めています。ただし、その成果はパレスチナ自治政府の改革や現場の治安状況に大きく左右されるため、今後の行方はまだ不透明です。
一方で、この判断がイスラエルへの外交圧力となり、停戦交渉や二国家解決の枠組みを前進させる可能性も十分にあります。日本としては、G7内での調整役として人道支援や制度設計の分野で存在感を示すチャンスでもあります。
結局のところ、この動きが「交渉の地ならし」になるのか「対立の固定化」につながるのかは、これから数年の国際政治の展開次第です。
それではまた、次の記事でお会いしましょう。
参考リンク
Reuters|Australia to Recognize Palestinian State at UN General Assembly (2025年8月11日)
Washington Post|Australia joins Western allies in recognizing Palestine (2025年8月11日)

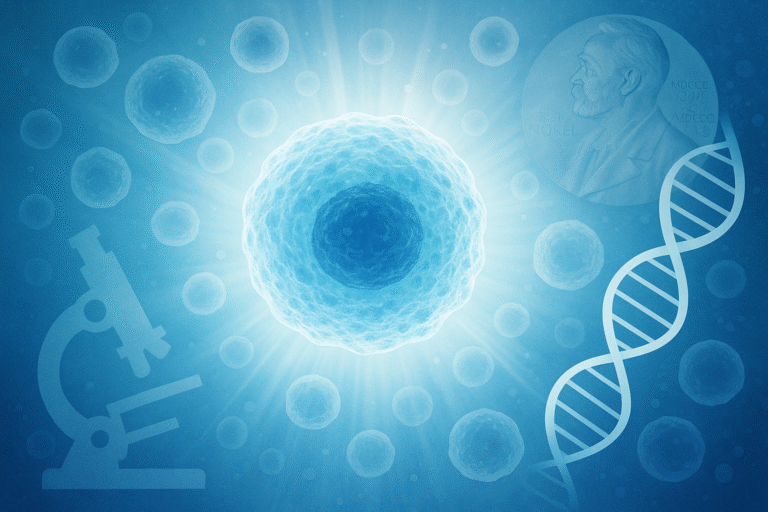

[…] 【海外の反応】オーストラリアがパレスチナ国家承認を表明:G7の外交転換と国際社会の現状 […]