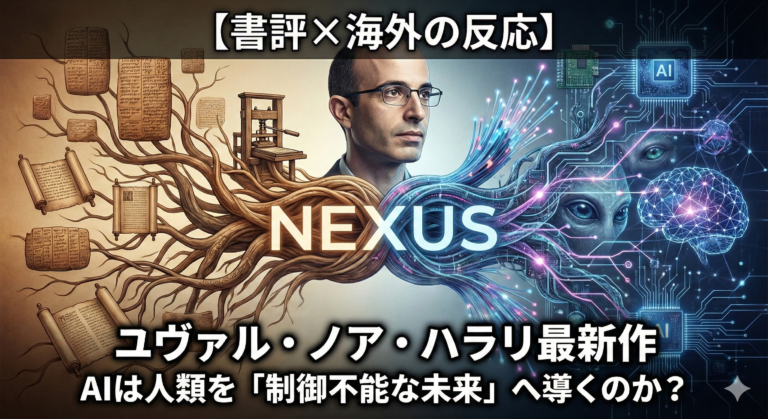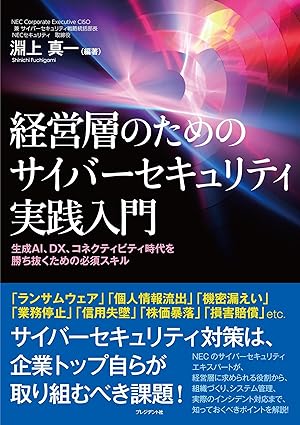
ニュースとの関連
生成AIの台頭、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速、そして国際的なサイバー戦の激化。
こうした時代において、「セキュリティは技術ではなく経営判断である」というテーマを正面から扱ったのが本書です。
NECのCISOである淵上真一氏を中心に、現場経験豊富なセキュリティリーダーたちが執筆。
経営者が「何を知らなければならないのか」「何を決めなければならないのか」を明快に整理しています。
アサヒビールの事例のように、企業活動が一瞬で止まる時代。
“知らなかった”という言い訳が通用しないことを、経営層自身が理解する必要があります。
そのための“教養と実践の架け橋”となるのがこの本です。
書籍の概要
序章では「そもそもサイバーセキュリティとは何か」を定義し、
第1章で現状とリスク構造を明示。
第2章〜第5章では、経営層が取るべき戦略・組織づくり・システム管理・インシデント対応を順に解説しています。
特筆すべきは「ガバナンス(統治)」の視点。
経営層は、セキュリティ対策のすべてを理解する必要はないが、
「誰がどこまで責任を持つのか」「判断材料をどう整理するのか」を明確にしておく必要があると説きます。
また、NIST CSF(サイバーセキュリティフレームワーク)をわかりやすく噛み砕いて解説し、
企業の成熟度に応じた実践ステップも提示。
専門知識がなくても理解できる構成でありながら、内容は高度です。
印象に残ったポイント
特に心に残ったのは、「被害を防げる企業は存在しない。勝負は“どれだけ早く復旧できるか”だ」という一節。
これはまさに、アサヒ事件にも通じる現実です。
また、セキュリティを「コスト」ではなく「経営資源」として再定義する姿勢にも共感しました。
複数の著者による実体験ベースの知見も豊富で、
経営層だけでなく、セキュリティ部門・IT管理職にも非常に有益です。
「わかりやすさ」と「実務的な深さ」を両立している点が、他書にはない魅力です。
せかはんの考察
この本が優れているのは、セキュリティを“会社の文化”として根づかせる視点を持っていること。
防御ではなく、「組織を守り、継続させる判断」をどう行うかに焦点を当てています。
経営者と現場の“通訳”となる言葉が随所にあり、
IT用語に苦手意識を持つ人でもスッと理解できる構成になっています。
AIやクラウドが前提となった今、サイバー攻撃は国家間の競争手段にもなっています。
そうした環境で企業が生き残るためには、
「リスクを想定し、判断し、復旧する」スキルが必要です。
その基本を体系的に学べる本書は、
まさに“経営層のための防衛教本”と呼ぶにふさわしい内容です。
それではまた、次回の記事でお会いしましょう。