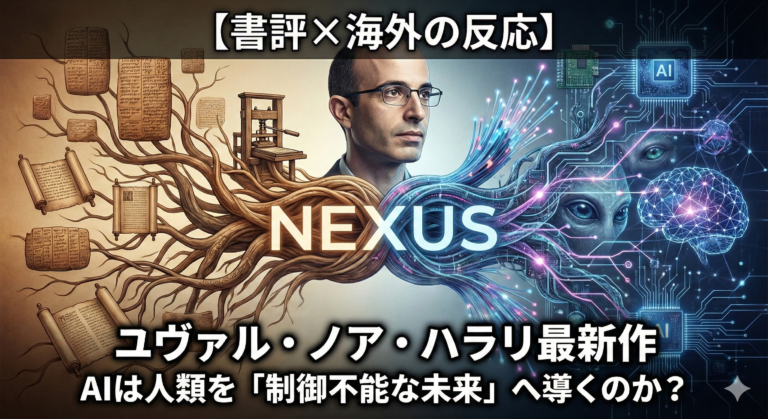ニュースとの関連
本書は、戦後日本政治の構造を「憲法をめぐる対立」という軸で貫き通し、占領期から現在の「ネオ55年体制」までを一気に読み解く一冊です。最近の自民党と維新の接近や、公明党離脱を契機とした政界再編の動きとも密接に関係しています。つまり、現在進行中の「保守再編」も、戦後から続く政治体制の延長線上にあるという視点を与えてくれるのです。
特に、立憲民主党と国民民主党の関係を、かつての社会党と民社党の関係になぞらえる分析は、現在の野党分裂構造を理解するうえで非常に示唆的です。戦後政治を通史で捉えることで、2020年代の日本政治が「例外」ではなく「繰り返しの歴史」であることが見えてきます。
書籍の概要
著者の境家史郎氏は東京大学法学部の准教授で、本書は同大学の授業内容をもとにした政治通史です。1945年の占領期から2022年までの政治の流れを、憲法を軸に整理しながら、保守と革新の対立構造、そして政治改革の波とその挫折を描いています。
内容は5つの章と終章から構成され、「戦後憲法体制の成立」から始まり、「55年体制」「改革の時代」「ネオ55年体制」までを通史的にたどります。戦後民主主義の下で生まれた自民党の一党優位体制が、民主党政権を経てもなお持続している理由を、「憲法というゲームのルールが変わっていないから」と位置づける点が特徴的です。
印象に残ったポイント
- 「55年体制」は1955年〜93年の保守合同から細川政権までを指すが、著者は実質的には60年代〜80年代を“安定期”と位置づけている。
- 民主党政権崩壊後、再び「自民一強+分裂した野党」の構図に戻った現状を「ネオ55年体制」と定義。
- 自民党は経済政策で柔軟に左派の主張を取り込みつつ、安全保障では保守を貫くという「現実路線」で支持を維持してきた。
- 野党はかつての社会党と同様、「護憲 vs 改憲」という構図に縛られ続け、政権交代可能な二大政党制が定着しなかった。
- 著者は現状を「改革の熱狂が去り、戦後の枠組みが再び前景化した」と総括している。
せかはんの考察
本書を読むと、「今の日本政治の行き詰まり」は新しい問題ではなく、70年以上前から繰り返されてきた“構造的宿命”であることが見えてきます。与党が柔軟に中道化し、野党が分裂するという流れは、社会の構造が変わらない限り続く――著者の指摘は冷静ですが、どこか絶望的でもあります。
それでも、著者が最後に示唆するように、「憲法をめぐる対立」から「経済・格差・地方」へと政治の軸が移る可能性は、希望の兆しとも言えます。まさに今、公明党の離脱や自民・維新の接近が話題となる中で、本書は「日本政治の現在地」を理解するための必読書です。
それではまた、次回の記事でお会いしましょう。