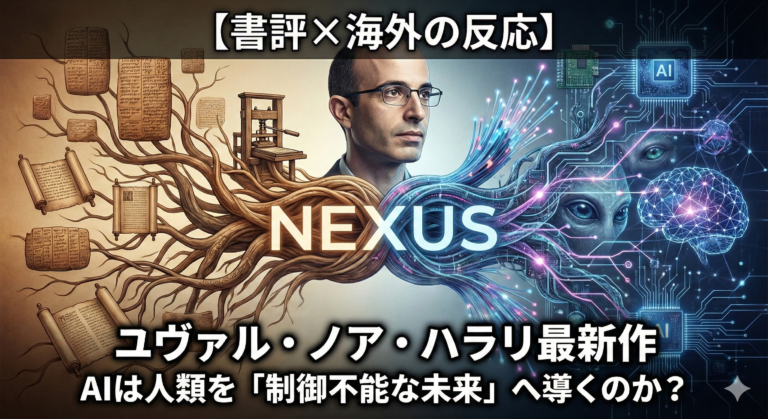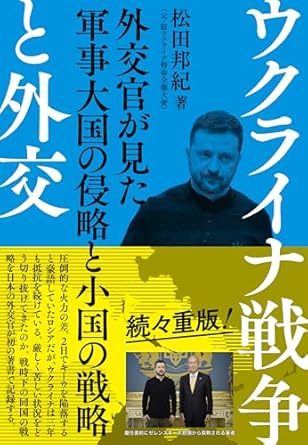
『ウクライナ戦争と外交 外交官が見た軍事大国の侵略と小国の戦略』
松田邦紀著(時事通信社、2025年5月2日刊)
ニュースとの関連
ロシアのウクライナ侵攻から3年以上が経過し、停戦の見通しは依然として立っていません。トランプ政権によるトマホーク供与中止や米露会談の見送りが続く中、改めて問われるのは「外交の力で戦争を止めることは可能なのか」という問題です。
本書は、2021年から2024年まで駐ウクライナ特命全権大使を務めた松田邦紀氏が、戦時下の外交現場を克明に記録した一冊です。戦火の中で行われた各国との調整や、現地の人々との交流を通じて、日本外交が果たしてきた役割と課題を描き出します。
書籍の概要
本書は、ロシアによる全面侵攻前夜からウクライナの抵抗、そしてG7による国際支援に至るまでの3年間を、外交官の視点から記録したノンフィクションです。
爆撃下での避難や、大使館再開に向けた苦闘、各国政府との緊迫したやり取りなど、ニュースでは伝わらない外交の裏側が臨場感をもって描かれています。
特に注目されるのは、G7議長国としての日本の立場と、岸田首相のキーウ電撃訪問をめぐる舞台裏。日本がどのように国際社会で信頼を築き、支援を具体化していったのかが克明に示されています。
印象に残ったポイント
- 現地大使館員たちが戦火の中でも職務を続けた、外交官の使命感と責任
- ウクライナの人々の強靭な精神と、国全体での抵抗のあり方
- 日本が軍事支援ではなく外交努力で国際的信頼を高めたプロセス
- 経済・文化支援を含む「総合的な外交」がいかに機能していたか
- 戦争を止めるための“現実的外交”と“理念的外交”のはざま
せかはんの考察
戦争報道が日常化し、数字や地名だけが消費される中で、この本は“外交官の目線”から「現場の人間の温度」を取り戻してくれます。
戦争を止めるには何が必要なのか、力の論理にどう向き合うのか。松田氏の記録は、単なる回想録ではなく「日本の立ち位置」を再考させる貴重な資料です。
トマホーク供与の中止や米露会談見送りといった最近の動きも、外交判断の難しさを物語っています。現場で苦悩した著者の言葉からは、「平和は努力なしには維持できない」という静かな確信が伝わってきます。
それではまた、次回の記事でお会いしましょう。