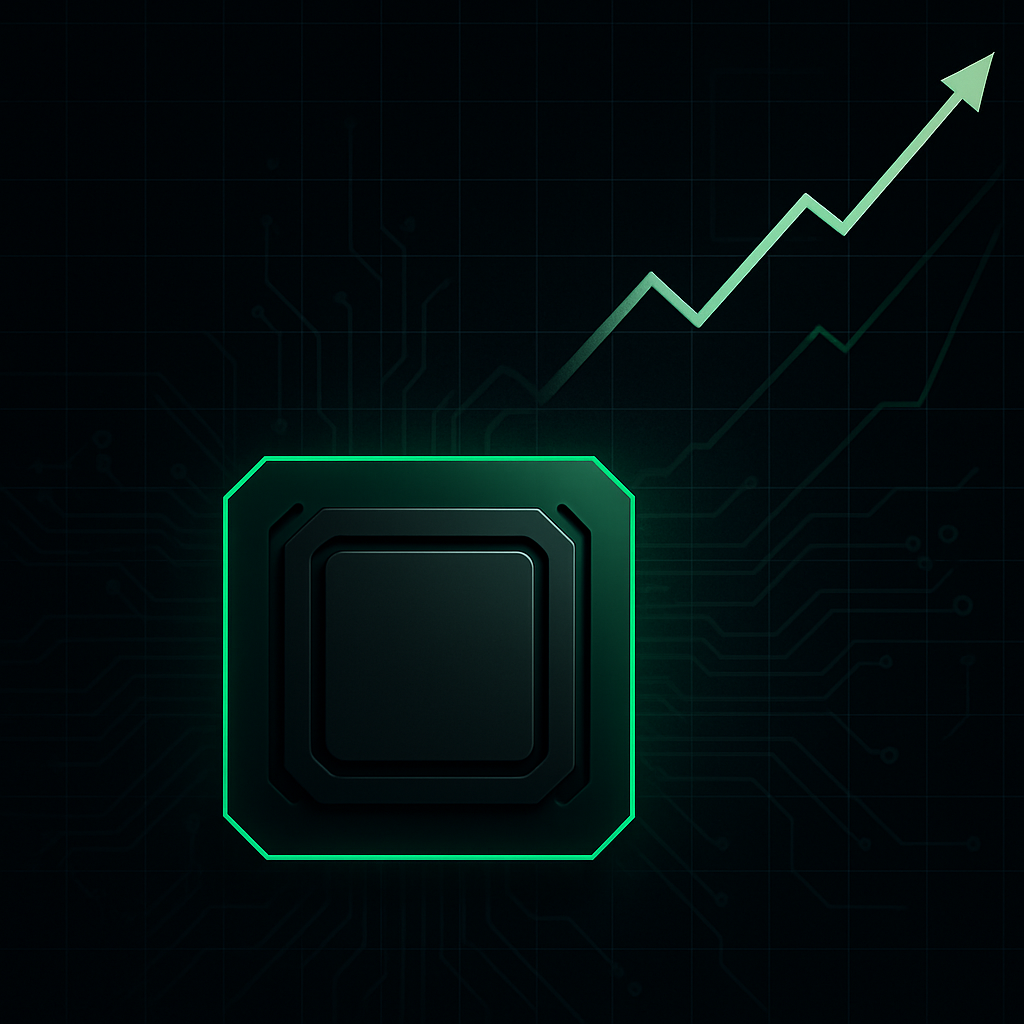ニュース
オーストラリア戦略政策研究所(ASPI)の「The Strategist」は、日本政府が非核三原則の扱いについて従来より柔軟な姿勢を示しつつあるとの見方を伝えた。報道では、安全保障環境の変化を背景に、日本が「核兵器を持ち込ませず」を含む三原則の今後の運用について、明確な方針を示さない場面が増えていることが紹介されている。
同記事は、こうした日本側の姿勢が日米同盟における核抑止の在り方を再評価する動きと重なる可能性を指摘。周辺国の軍備増強が続く中、三原則の厳格な運用が見直しの議論につながる余地が生まれているとしている。
関連記事
海外の反応
以下はスレッド内のユーザーコメントの抜粋・翻訳です。
戦争は嫌いだし、心から100%平和主義者なんだけど、バカじゃないつもりだ。ウクライナが核を手放さなければ、いまだに自国の領土を100%保てていただろう。日本よ、自分の土地と国民を守るために必要なことをしなさい。
これは事実だ。中国が近いうちに戦争を望んでいると思わないなら、それは愚かだ。しかも連中は文字どおりナチスみたいなものだ。ヒトラーが墓の中で中国の成功に怒り狂っていることだろう。
横須賀には、CSG-5(第5空母打撃群)が入港するたびに核が搭載されている。曖昧な説明でずっと否定されてきたけど、誰もが本当は分かっている。
ふむ……興味深い意見だ。だとすると、なぜ首相はさらに核ミサイルを受け入れようとしていると思う?今あるものでは不十分で、もっと必要だと考えているのだろうか?
海外の反応の続きはnoteで読むことが出来ます。
考察・分析
非核三原則が長く議論の的になってきた理由
日本の非核三原則は「持たず、つくらず、持ち込ませず」という三つの方針で構成されています。
このうち、特に議論が集中してきたのが「持ち込ませず」です。
日本は被爆国として非核を掲げる一方で、現実の防衛は米国の核抑止に依存しています。
つまり、日本は核を保有しないまま、米国の核の傘に入ることで安全保障を成立させてきました。
こうした二重構造が、三原則をめぐる議論が繰り返される大きな理由となっています。
さらに、冷戦期から現在に至るまで、米軍艦船が核を搭載しているかどうかを日本側が確認しないという慣行が続いたことで、原則と実態の間に一定の曖昧さが生まれました。
この曖昧さこそが、非核三原則と日米同盟の両立を支えてきた側面もあります。
東アジアの情勢が議論を再燃させている
2020年代後半に入り、周辺国の動きはこれまで以上に緊張を高めています。
中国は核戦力とミサイル戦力を拡大し、台湾周辺での軍事活動も活発化しています。
北朝鮮は戦術核の実用化を進め、日本を射程に収めるミサイル発射を繰り返しています。
さらにロシアはウクライナ侵攻に伴い核の威嚇を行い、世界的な抑止構造の前提そのものに不確実性が生じました。
こうした環境の変化により、日本国内では「アメリカの拡大抑止は本当に機能するのか」という懸念が強まり、三原則の運用を含む安全保障政策全体の見直しを求める声が高まっています。
世界で広がる「核保有論」という潮流
今回の海外の反応が過激に見える背景には、日本固有の事情だけではなく、世界的に“核を持たない国が弱者になりやすい”という認識が強まっていることがあります。
ウクライナが核を放棄した後に侵攻を受けた事例は象徴的で、
韓国、台湾、ポーランド、バルト三国などでも「自国は核を持つべきではないか」という議論が目に見えて増えています。
もちろん、各国政府の公式方針とは別の次元の話ではありますが、
国際フォーラムでは「核保有の是非」そのものがタブーではなくなりつつあり、
東アジアの緊張が強い地域ほど賛成意見が増える傾向があります。
日本に対しても、こうした“世界の温度感”が海外フォーラムでの容認論の強さにつながっています。
小泉防衛相が言及した「2010年の岡田答弁」とは何か
非核三原則をめぐる最新の議論の中で、注目が集まっているのが小泉防衛相の発言です。
政府の姿勢がどう変わったのかを判断するうえで重要なポイントとなりました。
小泉防衛相は会見で、非核三原則は政策として堅持するとしたうえで、
「持ち込ませず」の扱いについては2010年の岡田克也外相の答弁を踏襲すると述べました。
では、岡田氏は当時どのような説明をしたのでしょうか。
2010年の国会答弁で岡田外相は次のように述べています。
・非核三原則は原則として堅持する
・しかし、もし日本の安全保障が深刻に脅かされ、米国の核兵器の一時的な持ち込みを認めなければ国を守れないような非常事態が発生した場合
・その時の内閣が責任を持って判断し、国民に説明すべきである
つまり、三原則は維持するものの、国家存亡に関わる緊急事態では政治判断の余地が残されているという立場です。
小泉防衛相は今回、この従来解釈をそのまま引き継ぐと明確に述べました。
これは三原則の廃止や核共有へ踏み込むという意味ではなく、「従来の方針を維持したうえで柔軟性を確保する」という位置付けになります。
周辺国が神経質にならざるを得ない背景
日本の核政策は国内だけで完結する問題ではなく、地域の安全保障環境にも直結します。
特に中国、韓国、ロシアは日本の核に関する議論を敏感に受け止めます。
中国は歴史問題と安全保障を絡めて批判する傾向が強く、日本国内で核関連の議論が起きると国内向けに強く反発します。
韓国は歴史認識で摩擦がある一方、北朝鮮情勢を背景に日本との協力が必要となる複雑な立場にあります。
こうした地域情勢の中で、日本政府が三原則の扱いに慎重な姿勢を崩さない理由の一つとなっています。
総括
非核三原則は、被爆国としての道義と、現実の安全保障の間で維持されてきた日本の核政策の柱です。
小泉防衛相が示した「原則堅持」と「2010年岡田答弁の踏襲」は、そのバランスを保ち続ける従来の政府解釈を再確認したものであり、直ちに三原則を変更する動きではありません。
しかし、周辺国の軍拡や世界的な安全保障環境の不安定化を踏まえると、
日本の核抑止や三原則をめぐる議論は今後ますます重要性を増すでしょう。
日本がどこに柔軟性を残し、どこを守るのか。
その判断が、これからの安全保障政策の焦点になります。
それではまた、次の記事でお会いしましょう。
関連書籍紹介
『佐藤栄作-戦後日本の政治指導者』
村井良太 著(中公新書/2019年12月17日刊)
非核三原則を国の基本方針として確立した佐藤栄作とはどのような政治指導者だったのか、その実像に迫る評伝です。1960年代後半から7年以上にわたる長期政権期の政治判断を丹念に追い、沖縄返還、日韓基本条約、高度成長の歪みへの対応など、戦後日本の分岐点となった政策を幅広く取り上げています。
特に本書が示すのは、佐藤が「核を持たない日本」という国是をどのように形づくり、米国との関係や地域情勢の中で、現実主義と理念のバランスをどのように保ってきたのかという点です。非核三原則の成立過程を理解する上でも、本書は欠かせない視座を提供してくれます。
戦後日本の安全保障の基盤がどのように構築されたのかを知るうえで、非常に示唆に富む一冊です。
『「核抑止論」の虚構』
豊下楢彦 著(集英社新書/2025年7月17日刊)
核抑止は本当に安全をもたらすのか。この問いに対し、国際政治学者の豊下楢彦氏が、冷戦期から現在までの核戦略の歴史を踏まえて「抑止論は本質的に幻想に過ぎない」と論じた一冊です。
ロシアの核威嚇、北朝鮮の核開発、イラン問題、イスラエル情勢、そしてトランプ大統領の再登場。世界が再び核リスクの時代に入りつつある中で、核抑止論が抱える矛盾や「狂人理論」と呼ばれる危険な発想がどのように形成されてきたのかを、歴史的事例と論理分析を横断しながら明らかにしています。
非核三原則や核共有論を論じる際、抑止論の本質を理解するうえで示唆に富む内容です。
参考リンク
- Yoshida, F. “The International Implications of Japan’s Non-nuclear …” Global Governance Forum, May 2024. [PDF] https://www.globalgovernanceforum.org/wp-content/uploads/2024/05/I-Chapter-6.pdf
- Ota, M. “Conceptual Twist of Japanese Nuclear Policy.” Journal of Contemporary East Asia Studies, 2018. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2018.1459286
- Koketsu, A. “Japan’s Security Policy at a Turning Point: Prospects for the ‘Three Security Documents’ and Non-Armed and Non-Aligned Theory.” Meiji University ISC, August 2025. [PDF] https://www.isc.meiji.ac.jp/~transfer/papers/en/pdf/20/02_Koketsu.pdf
- Smyslova, A. “Nuclear Weapon in Changing World: The Realisation of Nuclear Sharing in Japan.” RECNA Nagasaki University, 2023. [PDF] https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/REC-PP-19.pdf
- Kase, Y. “The Costs and Benefits of Japan’s Nuclearization.” Non-Proliferation Review, 2001. [PDF] https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/82kase.pdf
- Japan Times. “Takaichi sidesteps commitment to decades-old nonnuclear principles.” Nov 12 2025. https://www.japantimes.co.jp/news/2025/11/12/japan/politics/takaichi-nonnuclear-principles/