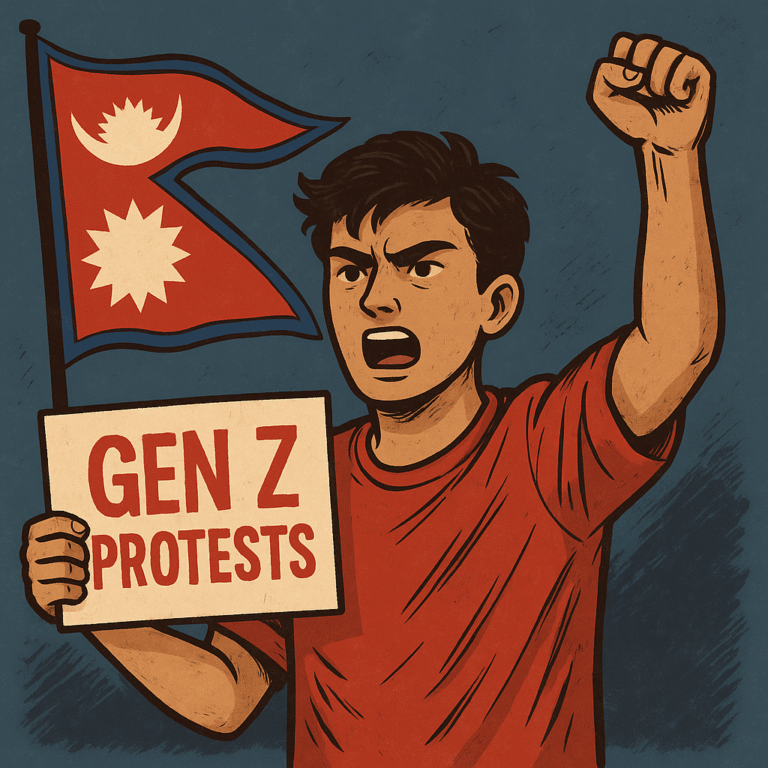防災の日と地震予知の変化
9月1日は「防災の日」。関東大震災の発生日にちなみ、災害への備えを見直す日として定められています。
かつて日本では「地震は予知できる」という期待が強く、1970年代から90年代にかけては前兆現象の研究や大規模な予知プロジェクトが推進されてきました。しかし2000年代以降、科学的に「地震の発生時刻や場所を短期的に正確に予知することは不可能」という見解が主流となり、2013年には政府も「予知は困難」と公式に認めています。
その代わり、現在は「30年以内に発生する確率」といった長期予測や、リアルタイムの観測・速報システムに重点が置かれています。緊急地震速報や津波警報などはその代表例であり、これは世界でも類を見ない高度なシステムです。
海外の反応
I’m considering moving to Japan and I’m too anxious about earthquakes since it’s a pretty much normal thing in Japan. What’s your feelings about this? How often does it hit? Is that really something I should think about or it isn’t that scary and dangerous? Please share your thoughts and experiences, I’d love to hear them
「日本に移住しようかと考えてるんだけど、地震が日常茶飯事みたいで不安なんだ。みんなはどう感じてる?どのくらいの頻度で来るの?本当に怖がるべきことなのか、それともそこまで危険じゃないのか?みんなの経験や意見をぜひ聞きたい」
I sometimes wonder which is better for peace of mind: living in Japan, where earthquakes are common, or living in a country where gun crime and robberies are common?
I know that’s like comparing apples and oranges, though.
「日本みたいに地震が多い国に住むのと、銃犯罪や強盗が多い国に住むのと、どっちが心穏やかに過ごせるのかなってたまに思うよ。まあ、全然別物を比べてるってわかってるけどさ」
Having lived in both, I can say with 100% certainty that I prefer Japan. Earthquakes are nothing compared to waking up with a gun pointed at you.
「両方の国で暮らした経験から言うと、間違いなく日本の方がいい。地震なんて、銃を突きつけられて目が覚めるのに比べたら大したことないよ」
I feel the same way. I rather die to a natural disaster than getting mugged and shot.
「同感だね。強盗に撃たれるより、自然災害で死ぬ方がまだマシだと思う」
I mean if you’re statistically going there; better be afraid of lightning strikes, airplanes falling out of the sky, getting hit by a car, stomach cancer….
「統計的に考えるなら、地震よりも落雷とか、飛行機が落ちてくるとか、交通事故や胃がんの方を怖がった方が現実的かもね」
Tiny ones might happen often (idk maybe every 3-8 weeks), bigger almost never. You deal with it by preparing an emergency bag, stashing some water/food, have your phone charged before going to bed and know the emergency place nearby (most likely a school). I even got a helmet 😂😏
… Honestly, better not to think about it much.
You should be aware though that a bigger one might hit big parts of Japan within next 30 years, but Japan tries to prepare for that already. It shouldn’t be a reason for you to not come here though.
「小さい地震はけっこう頻繁に起きる(3〜8週間に一回くらい?)、でも大きいのはめったにないよ。非常用バッグを準備して、水や食料を少し備蓄して、寝る前にスマホを充電して、近所の避難所(だいたい学校)を確認しておけばOK。俺はヘルメットまで持ってる😂😏
…正直あまり気にしない方がいいと思う。ただし、日本全体を揺らす大地震が30年以内に起きる可能性は高い。でももう国が準備を進めてるし、それで日本に来ない理由にはならないよ」
People are trying to prepare for it, but are actually very scared of it. Since 2011 every bigger shake results in panic-tweets online “I hope its not the big one 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲”
「みんな備えようとしてるけど、やっぱり南海トラフ地震はすごく怖がられてるよ。2011年以降、大きめの揺れが来るたびにTwitterで『これが本番じゃありませんように🥲🥲🥲』って投稿が溢れるんだ」
It will 100% happen. The question is just when. We have just to stay prepared, that’s all.
「必ず起きる。ただ“いつか”ってだけの話。だから備えておくしかないんだよ」
Look for an apartment complex build in the past 15 years, west of Shinjuku where you are on the rocky underground… Avoid old areas with tiny roads and small wooden houses… Avoid reclaimed land in Tokyo Bay because the ground liquification risk is high… Also, visit an emergency drill center to experience a Shindo 7 earthquake.
「東京なら過去15年以内に建てられた新しいマンションを探すといい。特に新宿の西側は地盤が固いから安心。逆に、細い道や木造住宅が密集する下町エリアは火事のリスクが高いし、埋立地は液状化の危険があるから避けた方がいい。あと、防災体験館に行って震度7を体験しておくのもおすすめ」
It’s not that bad. You’ll have to take part in lots of drills… My partner was the same as you initially — very scared about them — but now after three years here even they just say “oh an earthquake,” and we get on with whatever we were doing.
「そんなに大したことじゃないよ。防災訓練にたくさん参加することになるけど。うちのパートナーも最初は君と同じでめっちゃ怖がってたけど、3年経った今では“あ、地震だね”って言って、そのまま普段通りに過ごしてるよ」
Honestly most of the time you will sleep through them or not even notice them… Japan does a better job of disaster preparation I feel.
「正直、ほとんどの地震は寝てて気づかないか、揺れに気づいても気にしないくらいだよ。ただ、どんな災害でもそうだけど、食料や水、バッテリーを備えておくと安心感が違う。アメリカの地震多発地帯で育ったけど、日本の方が防災準備はずっとしっかりしてると思う」
Download the NERV app. It has real-time data… includes a really cool countdown timer that will let you know when and how intense the shaking… you’ll get 30-60 seconds advanced notice.
「“NERV”アプリをダウンロードしてみなよ。リアルタイムで地震情報を見られて、何秒後にどのくらい揺れるかまでカウントダウンして教えてくれる。30〜60秒前に通知が来ることもあるから、その間に行動できるんだ」
I basically don’t worry about it. We picked a part of Japan where earthquakes and tsunami are less common… Meanwhile there have been more earthquakes this week in the city we used to live in than we have experienced in 5 years in Japan.
「基本的に地震のことは心配してないよ。日本でも地震や津波が少ない地域を選んで住んでるから。実際、前に住んでた街では今週だけで5回以上地震があったけど、日本に引っ越してからの5年間で体感した地震はそれより少ないくらい」
Best to live in a place built according to the newest earthquake regulations. Earthquakes happen everyday here, but they are mostly very small and unnoticeable.
「最新の耐震基準で建てられた場所に住むのが一番いいよ。日本では毎日地震があるけど、そのほとんどは小さすぎて気づかないレベルだから」
備えの変化 ― 「予知」から「減災」へ
過去には「いつか予知される大地震に備える」という発想が支配的で、行政主導の避難訓練や備蓄が中心でした。
しかし阪神淡路大震災や東日本大震災を経て、「災害は必ず起きるもの」という認識が広がり、社会全体の考え方が大きく変化しました。
現在では、
- 自助(個人・家庭での備蓄や家具固定)
- 共助(地域や近隣の助け合い)
- 公助(政府や自治体の支援・情報提供)
の三本柱が防災の基本とされ、特に「自助」「共助」の重要性が強調されています。
個人や家庭が非常食やモバイル電源を備えるだけでなく、地域コミュニティが避難所運営や安否確認の訓練を行い、行政はハザードマップや避難所情報を公開するという役割分担が広がっています。
家庭に常備するための防災グッズはこちらからどうぞ
日本は防災先進国か?
日本はしばしば「防災先進国」と呼ばれます。これは、自然災害の多発という宿命を背負いながら、度重なる経験を通じて防災技術や制度を世界的に高い水準に発展させてきたことを意味します。
具体的には、
- 世界最先端の警報システム(緊急地震速報・津波警報)
- 厳格な耐震建築基準(1981年以降の新耐震基準など)
- 防災教育(学校での避難訓練や授業)
- 国際的な防災貢献(国連防災世界会議、仙台防災枠組み)
が挙げられます。
これらは世界的にも高く評価され、日本の防災モデルは多くの国に共有・輸出されています。
それでも残る課題
1. 経済的持続性と防災格差
高度なインフラ整備や耐震補強には莫大なコストがかかり、都市部と地方、富裕層と低所得層で「防災格差」が生じています。免震ビルに住む人と、古い木造住宅に住む人では、同じ地震でも被害が大きく異なるのが現実です。
さらに、2024年の能登半島地震では、道路や水道などのインフラ復旧が遅れ、「地方ほど復旧力が弱い」という課題が浮き彫りになりました。道路網の寸断で救援物資が届かず、ライフラインの完全復旧には数カ月から年単位を要しています。
復旧までの数日間に備えて、各家庭で電源や水を確保しておきましょう。
2. 社会心理と文化
「正常性バイアス」(自分だけは大丈夫と思う心理)により避難が遅れたり、備蓄を怠ったりする傾向が強くあります。また「公助」に依存する意識も根強く、理念としての「自助・共助・公助」が必ずしも実践に移されているわけではありません。
3. 高齢化と人口減少
避難困難者の増加や地域の担い手不足は深刻です。消防団や自治会の人員不足、過疎地での災害対応力の低下は、今後の大きなリスクとなります。
4. インフラの老朽化
近年、首都圏を含む各地で道路の陥没事故や水道管の破裂事故が相次いでいます。地震がなくても起こるこれらの事故は、地下インフラの老朽化が進んでいることを示しています。
日本のインフラの多くは高度経済成長期に整備されたもので、耐用年数を超えつつある施設が急増中です。能登地震での復旧遅れも、この「老朽化したインフラが災害時に脆弱になる」という現実を突きつけました。
5. 外国人・観光客対応
訪日外国人や在留外国人への多言語対応が十分とはいえません。災害時に外国人が適切に避難できる体制はまだ整備途上です。
6. 気候変動と複合災害
近年は地震だけでなく、台風の巨大化や集中豪雨、熱波などが頻発しています。防災は「地震対策」だけでは不十分で、「気候危機」への対応と統合して考える必要があります。
7. 国際的な双方向の学び
日本は世界に防災ノウハウを提供していますが、逆に海外から学べる点も少なくありません。ヨーロッパの洪水対策やアメリカのFEMAの制度など、相互に学び合う姿勢が今後さらに重要になります。
総括
日本は間違いなく「防災先進国」と呼べる存在です。地震や津波という避けられない自然の力に何度も直面しながら、そのたびに制度や技術を進化させ、世界に先駆ける取り組みを行ってきました。
しかし、防災は「完成」するものではなく、常に社会の変化や新たなリスクに対応して進化させる必要があります。高齢化、外国人対応、気候変動といった新たな課題にどう取り組むか――それこそが、今後の「防災先進国・日本」が試されるポイントになるでしょう。
それではまた、次の記事でお会いしましょう。