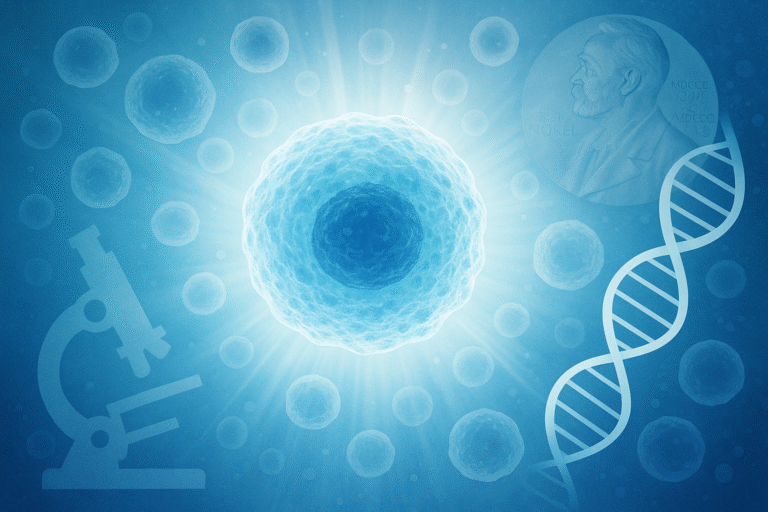海外の報道
「Japan marks 80th anniversary of WWII surrender as concern grows about fading memory」
日本は2025年8月15日、第二次世界大戦終戦80周年を迎え、300万人以上の戦没者に追悼を捧げた。石破茂首相は「反省(remorse)」という言葉を使い、2013年以来首相が避けてきた表現を用いた演説を行った。「戦争の悲劇を二度と繰り返さない」と訴え、戦争を知らない世代への記憶の継承の必要性を強調した。式典は武道館で行われ、正午に1分間の黙祷が行われた。安倍晋三以来、訪問を控えていた靖国神社への参拝は行われず、かわりに小泉進次郎農相が参拝し、中国・韓国から批判を受けた。毎日新聞は、戦前への歴史修正主義や「沖縄戦の民間人犠牲」や「南京大虐殺」への否認に懸念を示し、平和構築に向けた真摯な姿勢を求めた。
出典: AP News
「Japan minister joins crowds at controversial shrine to mark 80 years since World War Two defeat」
2025年8月15日、日本は第二次世界大戦敗戦80周年を迎えた。小泉進次郎農相が靖国神社を訪れ、2万5千人以上の戦没者とA級戦犯14名を祀るこの神社への参拝が、外交問題となっている。石破首相と天皇は別の式典に出席し、首相は靖国へ供物を送った。中国や韓国は同神社を日本の戦争責任回避の象徴とみなし、訪問を批判している。一方、両国関係では、8月23~24日に韓国大統領李在明が来日し、地域の安全保障や日米韓協力が議題となる予定だ。
出典: Reuters
「Hiroshima marks 80 years since atomic bombing」
広島では8月6日、原爆投下80周年を迎え、55,000人以上が出席した追悼式が開かれた。黙祷、白い鳩の放鳥、犠牲者への献花が行われた。被爆者の平均年齢は86歳以上となっている。被爆者グループ「日本被団協」はノーベル平和賞受賞の実績を活かし、核兵器廃絶への訴えを強めた。国連事務総長グテレス氏や広島市長は核拡散の危険と教訓を訴え、世界の指導者たちに核兵器への依存を見直すよう促した
出典: ポリティコ
玉音放送までの流れ
- 8月6日 広島に原爆投下
- 8月8日 ソ連が対日宣戦布告、満州侵攻開始
- 8月9日 長崎に原爆投下
- 8月10日 日本政府が条件付き降伏案を連合国に通達(国体護持)
- 8月12〜13日 軍部強硬派が抗戦継続を主張
- 8月14日深夜 宮城事件(クーデター未遂)、玉音放送レコード盤の奪取未遂
- 8月15日正午 玉音放送が全国放送され、無条件降伏を正式表明
海外SNSの反応
- 「あの玉音放送は、当時の日本人にとっては生まれて初めて天皇の声を直接聞く瞬間だったんだよね。しかも、その声が“戦争の終わり”を告げるものだったわけで、その衝撃は想像を超えるものだったと思う。」
- 「広島への原爆投下からわずか3日後に長崎、さらにその間にソ連が参戦…日本の指導部としては、もう決断を先送りする余地はなかったはず。外からの圧力が一気に二方向から来た感じだ。」
- 「“聖断(天皇の決断)”って言葉は美しい響きがあるけど、実質的には軍部の強硬派を抑えるための最後のカードだったんじゃないかな。天皇が直接介入しない限り、戦争はずるずると続いていた可能性が高いと思う。」
- 「宮城事件っていうクーデター未遂のことを知ってる人、海外だとほとんどいないよね。戦争が終わる直前に、軍人たちが玉音放送を阻止しようと動いたなんて、映画みたいな話だ。」
- 「“国体護持”を降伏条件に入れたっていうのは、日本にとって本当に譲れない最後の一線だったんだなと思う。それを守れなかったら、降伏そのものが受け入れられなかっただろうね。」
- 「玉音放送の日本語は古典的で難しくて、当時の国民の多くはすぐに意味を理解できなかったらしい。『耐え難きを耐え…』とか文学的すぎて、ラジオの前で混乱した人も多かったと思う。」
- 「原爆が降伏の決定打だったのか、それともソ連の参戦だったのかって議論は、海外の歴史フォーラムでもずっと続いてる。多分、答えは“両方”なんだろうけど、どっちを重く見るかで意見が割れる。」
- 「もし宮城事件のクーデターが成功していたら、玉音放送は全国に流れなかったかもしれない。そうなると、戦争はさらに長引いていた可能性がある…そう考えると本当にゾッとする。」
- 「玉音放送のレコード盤を必死で守った人たちは、ある意味で日本の未来を救った英雄だと思う。もし破壊されていたら、降伏の意思が国民に伝わらず、国内はもっと混乱していたはず。」
- 「『耐え難きを耐え…』っていう表現は、ただの文学的な言い回しじゃなくて、政治的にも計算され尽くした言葉だった気がする。敗戦を受け入れる一方で、国民の尊厳を守ろうとする意図が感じられる。」
地政学的背景と分析
記憶継承の危機
戦争を直接知る世代が減り、記憶の継承は年々難しくなっている。今回、石破首相が久々に「反省」という言葉を用いたのは、節目の年としての重みと、次世代へのメッセージを意識した行動といえる。
靖国参拝の外交的摩擦
次期首相候補筆頭とされる小泉農相の靖国参拝は、日中・日韓関係に再び歴史認識の影を落とす可能性がある。今後予定されている首脳会談にも、微妙な緊張を与えかねない。
原爆と冷戦の構図
海外の議論では、「原爆よりもソ連参戦が降伏の決定打だった」という意見が目立つ。戦争終結の背景には、冷戦の幕開けという新たな国際秩序の形成が密接に絡んでいた。
核廃絶と現実の乖離
広島・長崎から発信される核廃絶のメッセージは国際的な共感を呼ぶ一方、日本は依然として米国の核の傘の下にあり、理想と安全保障上の現実との隔たりは大きい。
80年の平和と現代の不穏な現実
日本国内にいると、この80年間を「平和が続いた」と感じがちですが、世界の視点で見ると、戦争は絶え間なく続いてきました。冷戦下の朝鮮戦争やベトナム戦争、中東紛争、そして21世紀に入ってからのアフガン戦争やイラク戦争、シリア内戦、ロシアによるウクライナ侵攻――いずれも数十万人から数百万人の命が奪われています。
今もウクライナでは砲撃が止まず、ガザでは市街戦が続き、アフリカのスーダンやサヘル地域では内戦とテロが拡大しています。平和は国境の外では当たり前ではなく、日本の「戦後平和」はむしろ例外的な環境と言えるでしょう。
一方、東アジアの安全保障環境も急速に変化しています。台湾海峡では中国軍機・艦艇の活動が活発化し、米中間の軍事的緊張が高まっています。台湾有事が現実化すれば、日本の南西諸島や沖縄、さらには本土も戦域に巻き込まれる可能性があります。
80年前の世界大戦は、植民地支配や資源争奪、民族独立運動といった要因が火種となりました。しかし、もし第三次世界大戦が起きるとすれば、その原因は全く異なるかもしれません。技術覇権をめぐる争い、エネルギーやレアメタルの供給制約、サイバー攻撃や宇宙空間での軍拡競争――新しい時代の戦争は、より多様で複雑な引き金を持つでしょう。
戦後80年の節目は、過去の悲劇を思い出すだけでなく、現在進行形の危機を直視し、次の80年をどう守るかを考える出発点でなければなりません。
それではまた、次の記事でお会いしましょう。