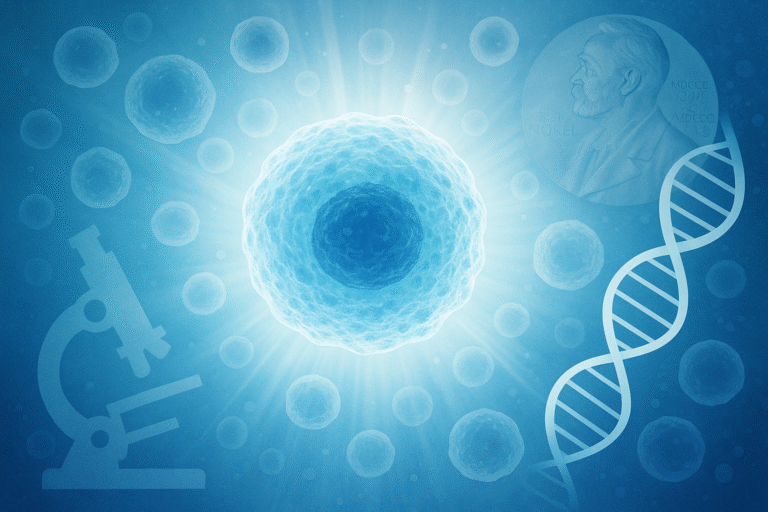日本で相次ぐ転売騒動:Switch2・ポケモンカードが標的に
最近、日本では任天堂の新型「Switch2」や、マクドナルド限定のポケモンカードが発売直後に瞬時に売り切れ、フリマアプリで高額転売される事例が相次ぎました。消費者からは「本当に欲しい人が買えない」「子供の楽しみを奪っている」といった批判の声が上がり、SNS上でも大きな議論を呼んでいます。
こうした事態は日本に限らず、世界各国でも同様に発生しており、「転売は市場を歪める迷惑行為なのか」「それとも資本主義の一部として正当なのか」という論点で議論が交わされています。
海外の転売規制:イギリス政府がチケット転売を制限へ
イギリスでは、人気コンサートやスポーツイベントのチケットが即座に売り切れ、高額で転売される問題が深刻化しています。これを受けて政府は、転売価格を定価の30%までに制限する新ルールを検討中です。違反した業者や販売サイトに罰則を科す方針で、消費者保護の観点から規制強化の流れが加速しています。
経済学から見た転売の役割
一方で経済学者の中には、転売が市場の効率化に寄与していると評価する声もあります。人気商品の需要が供給を上回る状況では、価格を通じて商品が本当に必要な人へと再配分される仕組みが働きます。
「転売は単なる悪ではなく、需給ギャップを埋める市場機能の一部」とする議論も存在するのです。
Redditで盛り上がる「転売」議論
Hey everyone, Just wanted to open up a real conversation because I’ve been feeling it hard lately — and I know a lot of you are too.
I saw a post from a fellow full-time reseller who’s been grinding for 4+ years… and this past year hit harder than ever.
Lower sales.
Higher shipping costs.
Inventory moving slower.
Platforms like Poshmark, Depop, and Etsy just aren’t what they used to be.
And honestly? It’s starting to feel like the whole reselling game has shifted.みんな聞いてくれ。最近キツいなって本気で感じてて、同じ人も多いはず。
フルタイムで4年以上やってる仲間の投稿を見たけど、今年は過去イチで厳しいって。
売上は落ちる、送料は上がる、在庫は動かない。
Poshmark、Depop、Etsyも前みたいには売れない。
正直、転売のゲーム全体が変わっちゃった気がしてる。
People want deals. I keep average cost of goods below 2 dollars and sell high volume at 12ish dollars profit per sale. It’s a grind, but the days of moving mid level brands at 20 plus dollars profit is dead.
みんな「お得」を求めてる。仕入れ単価は平均2ドル以下に抑えて、1件あたり12ドル前後の利益で回転重視。体力勝負だけど、中堅ブランドで1件20ドル超の利益がポンポン出る時代は終わったね。
I have the opposite approach to sourcing inventory but the everyone wants deals piece on the selling end is 100% key on either end. My net margins are barely over 50% but my average cost for each deal is about $200 and so there is a lot of meat on the bone and it’s desirable stuff that sells fast for high prices. I don’t have a massive inventory and make a full time living with this approach I do make a worse ROI but see that return within a week but I always go into a buy figuring I will undercut the market slightly to offer a deal and get my money out of it faster.
自分は真逆の仕入れスタイル。でも「買い手はディールを求めてる」って点は100%同意。純利はちょい50%超くらい、1件の仕入れは平均200ドルで“旨味”が大きい人気商品を狙う。大量在庫は持たず、このやり方で専業。ROIは低くても回収は1週間以内。仕入れる時点で相場より少し安く出して、早く現金化する前提で動く。
Yeah the “Deal” is I found something you couldn’t and I pay all the high fees. That’s all you are getting or kick rocks.
そう、“ディール”ってのは「俺があんたに見つけられない物を見つけて、高い手数料まで払ってる」ってこと。欲しきゃそれで取引、嫌なら他所へどうぞ。
Good, those days just inflated prices for no reason.
それでいい。根拠もなく相場を吊り上げてた時代は終わりでしょ。
I’ve seen this topic come up a lot lately, and I think I have a slightly different perspective. I’ll start by saying I’ve only been reselling for almost two years, but I’ve consistently held what I would consider an average to above-average number of sales. My 90-day total has never dropped below $30,000, and my ROI usually sits around 60% or higher.
この話題、最近よく見るけど、私は少し違う見方。転売歴はまだ2年弱だけど、売上は平均〜やや上くらいを安定維持。直近90日で3万ドルを切ったことはなく、ROIはだいたい60%以上。
In my opinion, the biggest cause of what’s happening isn’t just the economy — it’s the rise of tools like Google Lens and the constant social media push about how much money you can make reselling. Everyone is out “reselling” now, and that’s caused major oversaturation across a lot of categories. The old mindset of “everything sells eventually” is gone.
今の状況の主因は景気だけじゃなくて、Googleレンズみたいなツールの普及と「転売は儲かる」ってSNSの煽り。みんな参入して供給過多、昔の「そのうち売れる」はもう通用しない。
Today’s tools — keywords, SEO, better lighting, AI-driven optimization — are right at our fingertips. Sellers who are adapting are thriving.
いまやキーワード、SEO、照明、AI最適化…使える武器は山ほどある。適応してるセラーは伸びてるよ。
Another major shift is that customers today expect a lot more. Good customer service matters now more than ever. Fast communication, clear descriptions, quick shipping, easy returns — all of that builds trust and loyalty. If you’re customer-centric and make the buying experience smooth, you’re already standing out from half the competition.
もう一つの変化は“客の期待値”の上昇。対応の良さが以前より重要。連絡は速く、説明は明確、発送は迅速、返品は簡単。これだけで信頼とリピートが生まれる。買い手目線を徹底すれば、競合の半分には勝てる。
We are living in a dreadful world. I’ve pivoted to selling items that make people happy.
しんどい世の中だよ。だから“人をハッピーにする物”に舵を切った。
Honestly the world’s been dreadful for a long long time so selling things that make people happy is an evergreen need.
正直、この世界はずっと前からしんどい。だから“人を喜ばせる物”は常に必要、普遍のニーズだね。
日本と海外で違う「転売観」
欧州:公平性を重視し規制強化
イギリスをはじめ欧州では「ファンの公平な機会」を重視する文化が強く、チケット転売規制のように消費者保護のための政策が進められやすい傾向があります。
米国:資本主義的自由として容認
スニーカーやゲーム機などの転売は、副業や生計の手段として社会的に一定の理解を得ています。「市場に需要があるなら正当」という考え方が根強いのです。
日本:倫理的批判が強い
日本では「転売ヤー」という言葉が定着し、社会的な非難が集中しやすい傾向があります。背景には「公平に分け合うべき」という文化的価値観があり、欧米とは対照的です。
まとめ:転売は「悪」か、それとも商売の基本か
日本では「転売ヤー」という言葉がすっかり定着し、多くの人が強い嫌悪感を抱いています。特にSwitch2やポケモンカードのように、本当に欲しい子供やファンが手に入れられない状況が繰り返されれば、「転売=社会悪」と考えるのは自然な感情です。さらに、コロナ禍のマスク不足や令和の米騒動のように、生活必需品を買い占めて流通を堰き止めた例は、明らかに社会を不安に陥れるものであり、強い批判が向けられて当然です。
ただし忘れてはいけないのは、「安く仕入れて高く売る」こと自体は、商売のもっとも基本的な形 だという点です。八百屋も書店も家電量販店も、すべては仕入れと販売の差益によって成り立っています。極端な買い占めや独占的な高額転売は確かに問題ですが、適正な範囲での商品再販は本来の商取引の一部なのです。
海外では、転売を一律に「悪」とせず、「規制すべき領域(必需品や公共性の強いもの)」と「市場に任せる領域(趣味や嗜好品)」を分けて議論 する傾向があります。日本でも、転売を無条件に忌避するのではなく、「どこまでが許されるか」という線引きを冷静に考えることが求められているのではないでしょうか。
転売は社会を混乱させる側面と、市場を効率化させる側面の両方を持っています。だからこそ、私たちは「感情的な嫌悪感」だけでなく、「本来の商売のあり方」と照らし合わせながら、その功罪を考える必要があるのです。
それではまた、次の記事でお会いしましょう。
おすすめ書籍
漫画 お金の大冒険 黄金のライオンと5つの力・【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学 2冊セット [ 両@リベ大学長 ]
あなたもAmazonで副業!初心者でも3日で稼げる転売の教科書【電子書籍】[ 良一 ]
メルカリ中国輸入転売のはじめかた 月5万円の壁を越える [ 瀬戸山エリカ ]